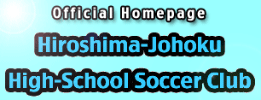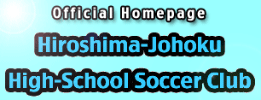12月15日 火曜日。
この日は地元のブラスバンドグループの演奏会があった。
7時からということで、6時には友達のパトリシアとカシアが僕を迎えに来た。
なんやかんやしゃべっていると6時半になり、出発しようとして図書館を閉めようとした瞬間、カロリーニが何か本を読んでいるのが目に入った。
カロは周りの空気に敏感な子なので、皆がそろそろカノアに行くのを知っていたはずで、普通なら言われる前に図書館から出ていただろう。
でも、カシアに言われても窓を閉められてもぎりぎりまで本を読み続けていた。
何の本なんだろう。
その本を見た時、全身が凍りついた。
「ブラジル人のための、日本語を学ぶ本」
時は少しだけ遡り、僕がメロン農園に行く前までは火曜日の18時からと土曜日の14時から、日本語教室を開いていました。
毎回5人くらいの日本語が好きな子達に教えていたのですが、メロン農園から帰ってきて色んなことが変わっていました。
まず何よりセントロ自体にほとんど人が来なくなっていて、日本語教室の生徒達も、日本語教室を開いていた時間になっても来なくなってしまったのです。
イベントや会議、仕事がその時間にたまたま重なったのも大きく、そんなこんなで日本語教室はストップしていました。
日本語が好きな彼女らに確認も取らぬまま。
そして、この日は火曜日。
18時半。
僕を含めた皆がカノアに行ってブラスバンドの発表を見ようとする中、図書館で一人、ただただ日本語の本を読むカロリーニ。
まるで何かを訴えかけるかのように。
そのささいなかつ恥ずかしがりやの彼女にとっては最大の努力であったのであろうサインを、僕は見逃すことなどできませんでした。
一瞬全てが止まり、僕はカロリーニに聞きました。
「日本語教室、待ってたの?」
彼女は何も答えませんでした。
頭がいい子だから、僕がカノアに行くことくらい想像していたのでしょう。
恥ずかしがりやで本当のことは口や態度にはほとんど出さないけど心はとても温かい子だから、自分の気持ちを抑えるだけでなく、周りの空気や僕のことまで考えてくれたんでしょう。
そんなけな気な彼女を放って、そんな懸命な小さなサインを放って、カノアに行くことなんてできませんでした。
もしかすると、彼女は今まで懸命にサインを送り続けていたのかもしれません。
そして僕は、その小さなサインに全く気付いてあげることができていなかったのでしょう。
時間がせまっていたのでこんなささいなことを細かく説明するひまなどなく、僕以外からしたら何も感じないことを理由に一緒に行くと約束したのを断るのは辛かったけど、断りました。
すぐに行くから。と言って、僕だけセントロに残りました。
「カロ、おいで!おれ行かないから、まだここにいていいよ。」
帰ろうとしているカロリーニにそう言うと、恥ずかしがっているのかそれとも他の何かなのかはわからなかったけど、はじめは中々部屋の中に入って来ませんでした。
帰るかどうか迷っていたのかもしれません。
でも僕は、彼女が求めていることを間違いなく受け取ったと信じていました。
だから、彼女のタイミングを待ち、入りやすい状態を作ってあげようと思い、できるだけ普通に装い、それでちょっとバカみたいに歌を歌って待ちました。
また、彼女は極度の照れ屋ということもあったので部屋に入る動機を作ってあげようと思い、僕は自分で作った日本語の教科書のコピーも準備して、「これやってみ。」と課題も与えてみました。
すると、カロは何事もなかったかのようにサッと僕の横のいすに座り、こう言いました。
「何やればいいの?」
最高の笑顔は心の中にしまいこみ、約2週間ぶりに日本語教室が始まった瞬間でした。
結局なんかしんみりした授業になってしまい、彼女にとっては雰囲気はもちろん内容も難しいようでした。
ということで気分転換。10円サッカーキックオフ。
小さい頃は机でよくやっていたものですが、3つのコインを使い、コインの間をパスでつなぎながら相手の指で作ったキーパーのいるゴールを目指す遊びです。
日本語には全く関係ないことでしたが、彼女の笑顔を見れただけでもこれは大成功だったんでしょう。
雰囲気がやわらかくなったところで、最後に日本語の歌を教えることにしました。
うみはひろいな、おおきいな。つきがのぼるし、ひがしずむ。
うみはおおなみ、あおいなみ。ゆれてどこまで、つづくやら。
うみにおふねをうかばせて。いってみたいな、よそのくに。
授業が終わると、カロが僕にこう言いました。
「明日の朝、ヘシクリアンサでサッカーのボードゲームしない・・・?」
「いいよ。」
僕が心の底から笑って答えると、不安そうなカロの顔が、満開の笑顔に変わりました。
2009年12月21日